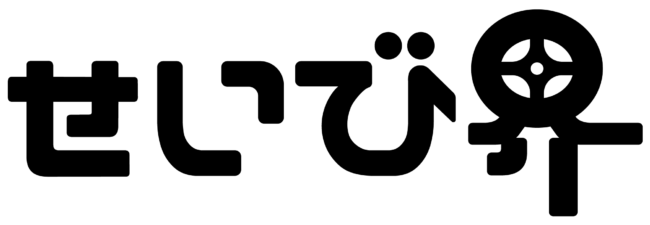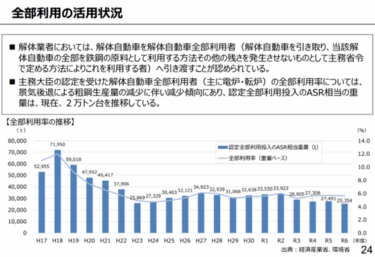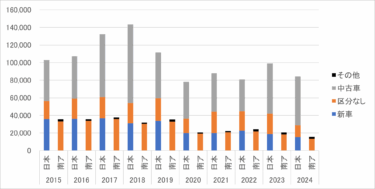熊本大学大学院人文社会科学研究部(法学系)・環境安全センター長
外川 健一
1.はじめに
一般社団法人日本自動車リサイクル部品協議会(以下、リ協)の前身である一般社団法人日本自動車リサイクル部品販売団体協議会(以下、協議会)の15年史が、2010年1月10日に刊行された。編集委員は委員長に北口賢二氏(会長・部友会)、副委員長に清水信夫氏(会長代行・自研会)、委員に大橋岳彦氏(理事・NGP)、深澤広司氏(理事・リビルト部品工業会)、針ヶ谷昌之氏(理事・テクルスネットワーク)、土居秀幸氏(理事・SAP)のほかに、永澤卓也氏(常務理事・事務局長)で構成されていたが、主として本書を執筆していたのは長く日刊自動車新聞社で記者として活躍し、この業界に転じた永澤氏であった。
当時副委員長であった清水信夫氏は、「この業界がしっかり社会に認知されるために、そして後進の者が歴史をしっかり知ることができるように、何とか自動車リサイクル部会業界史を編纂したい。しかし、それが書ける人は1人しかいない。当時還暦を迎えたいわゆる新聞社出身で、わかりやすい文章が書ける永澤氏だ。氏が現役である間に何とか業界史の変遷を書き残してもらいたい」と当時筆者に熱意をもって語ってくれた。委員長の北口氏も業界史の編纂に賛同した。そして筆者も寄付金をいただき、編集顧問として永澤氏を補助することになった。
永澤氏は、それから通常業務の時間の合間をみて、協議会発足以前からその経緯を観察、記録していたこともあり、業界人に興味深く読んでもらおうと苦心して執筆を1年強にわたって行った。特に永澤氏がこの業界に関わりあったのは1990年あたりからであり、当時の記録はいわゆるワープロの3.5インチフロッピーに保管されていた。このデータをパソコンへ読み込ませようと永澤氏は苦心し、私も何枚かのフロッピーディスクをテキストデータで変換できないか、大学関係者や福岡の業者に問い合わせたが、データの解読は困難だった。結局永澤氏はこれらのデータをプリントアウトしたり、リングファイルに閉じられた資料から重要なものを丹念に探して、再度パソコンに打ち直しながら原稿を作成していった。
リ協の現代表理事である川島準一郎氏は、現職を引き受けるにあたってこの15年史を読み直し、先人の苦労と自分たちがこれから業界を発展させていくために歴史から学ぶ必要性を感じ、JARAグループの北島宗尚氏とともに、一般社団法人化したのちの2010年からの15年史を創る必要性を感じて、リ協理事会にそれを提案・承認を受けた。そこで、SPNの齋藤徹氏が編集委員長となり、新たに編集委員会が立ち上がった。私も編集委員に加わることとなった。
そこで、今回は改めて前回刊行された永澤氏の力作である旧15年史を読み直して、読者の方々と一緒にリサイクル部品業界の歴史を振り返り、歴史から学んでいきたいと思う。
2.旧15年史を再読する(前半)
前半部分は業界一本化のための奮闘記。
旧15年史では、まずリ協では最古のグループであるビッグウェーブ関係者に焦点を当てている。
「投機に惑わされない中古部品屋」めざす後継者たち
この平成不況時期1980〜90年代、地域の自動車解体業者の後継者たちの中に、金属スクラップなど「投機に左右されない商売をやりたい」とする者たちが現れた。
彼らは、米国など自動車先進国を視察し、当時ディスマントラーと呼ばれた解体・中古部品業者、そして日本にはまだ無かった損害保険会社が主催する「中古車オークション」も初めて目にするところとなった。そうした者たちの一部は中古車販売事業を目指し、一部は近代的な中古部品販売業として取組む者たちがこの時期発生する。自動車解体業者による集団化を目指した若手の経営者たちは、「中古部品」をあらためて新たな経営の柱に育てようとしていた。
後述する、新たな部品流通団体「自動車解体部品同友会」(後のビッグウエーブの前身)の有力メンバーとなった福島県の中堅自動車解体業者有限会社菅野自動車商会の代表、菅野勇三もその一人だった。
菅野氏は、私費出版『夢をさがして-菅野勇三自伝』(1996年刊行)の中で、1972年(昭和47年)米国ロスアンゼルスへの研修旅行に参加、工場敷地内を貨物車が走るような巨大なスクラップ工場から、無線で仲間と商談を進める中古部品店まで、自動車先進国、米国での解体業の実態を見学、帰国後、スクラップ商売から徐々に撤退、中古部品業へ転換していく様子を物語っている(旧15年史、pp. 54-55)原文のまま。
この『夢をさがして-菅野勇三自伝』は、私も菅野氏にインタビュー調査に行った際にいただいたが、氏の実直な性格が表れた内容になっている。戦後の混乱期に、東北の若者が何とか貧困から抜け出すために、ひよこの鑑定士の資格を得るため奮闘する姿や、モータリゼーションの時代を目にして、自動車中古部品に目を付け、自動車解体の基礎を学ぶため上京し、そして若い仲間たちと新しいグループ(後のビッグウェーブ)を構想し、実現させるストーリーは読み応えがある。
京都で「自動車解体部品同友会」創設
その若手解体業の経営者の一団が、1979年(昭和54年)6月、京都に集まり「自動車解体部品同友会」を立ち上げた。菅野は、前述の自伝「夢をさがして」の中で、その当時の同友会立上げの模様をこう語っている。
「1979年(昭和54年)5月、『日本自動車解体部品協会』(注:当時の解体業全国団体のひとつ)の総会が東京で行われた。その後の懇親会で(菅野の)肩をたたくものがある。振り向くと京都の岡村(猛・オカムラ社長)、金沢の奥野(松方・奥野自動車商会社長)、神戸の西木(隆・西木産業社長)の三人である。(中略)三人は、自動車解体部品業界の現状と将来についてよく勉強しあっていた。(中略)俺たち若い者が、この業界の未来を何とか開いていかなければならないというのが、三人の大きな課題であった。(菅野と)三人は意気投合した。この業界は、このままでいいのか、これから先は何を目的に進めばいいのか、今何をすべきか、同じことを考え続けていたのだ。(中略)(菅野は)その席上で仲間を募った。東京の立川で初めて中古部品見せてくれた大谷(武司・大谷自動車部品社長)氏、雲出(利男・クモデ商店社長)氏、京都の樋口(隆雄・旭商会社長)氏、千葉の成田(巌・成田商店代表)氏らが集まった。その場で『青年経営研究会』なるものが結成されることになり、新しい絆(きずな)が生まれた。若手の解体業者が未来の方向を探す小さな勉強会ではあったが、これが後に、自動車解体業界にとっての大きな一歩になるのである」
この『青年経営研究会』のメンバーが核になり、79年(昭和54年)ビッグウエーブの前身「自動車解体部品同友会」を立ち上げたのであった。
初代会長には推挽(すいばん)により京都の岡村猛氏が就任した(旧15年史、pp. 55-56)原文のまま。
この部分の記述には、菅野氏が同じ思いを抱いた若手経営者と一緒に、新しい時代に即した自動車解体部品市場を拡大するために意気投合した姿が具体的に描かれている。
そして初代会長に選ばれたのは京都の岡村氏であったが、それは岡村氏のリーダーシップもあるが、やはり当時京都に、ポンコツ街道といわれた関西の自動車解体業者の集積があったことが背景にはあるのかもしれない。
一方、こうした動きは別の地域でもあった。
首都圏にはリビルトパーツクラブ生まれる
京都の動きに先んじる77年(昭和52年)、まったく違った視点から、首都圏の四人の自動車解体業者による勉強会が開かれていた。東京都保谷市の川澄商会の鍛政雄社長、埼玉県の清水商会の清水信夫専務、茨城県増田商会の増田英雄専務、山梨県の河村自動車工業の河村二四夫社長によるRPC(リビルトパーツクラブ)である。それぞれ商圏が離れている業者同士による「中古・再生部品交換会」がその狙いであった。後に清水商会の社長に就任した清水信夫は「当時、中古・再生部品という言葉をかっこよく見せようと、あまり深く考えもせずにリビルトとつけたんでしょう」と苦笑する。清水ら4人は、早くから「中古部品商」という視点での経営を目指し、全国の整備業を相手に部品販売を進めていた。
清水は「当然、自社の在庫だけでは対応できず、同業者間の在庫を互いに融通した方が便利と考え、同業者によるネットワーク化が不可欠と考えた」と「株式会社清水商会の沿革」の中で述べている(筆者注 永澤氏はここの部分を「株式会社清水商会の沿革」のコピーで書いており、正確な時期は不明である)。
最初は在庫情報の交換からスタート、時には現物の持寄りによる交換会になることもあった。それが次第にFAXによる在庫情報の交換へ、梱包・資材の共同調達から発送の基準作り、運賃コストの比較による輸送業者の共同利用までに発展する。
やがて東京で川澄商会の近くに住居を持ち「板金塗装新聞」を発行していた井上勝彦が、このRPCと中古部品のユーザーである板金塗装修理業界との橋渡し役になり、中古部品流通独特のノウハウが確立されていくことになる。
その間、後日NGPグループを立ち上げた大分県の大石一彦東邦物産社長が、RPCの勉強会に個人として参加、RPCのノウハウがNGPの組織活動に受け継がれていくことになる。
RPCの活動は83年(昭和58年)まで続けられた。同年ボディーパーツメーカー株式会社日豊製作所の外装部品代理店組織GBP(グッドボディーパーツ)設立とともにメンバーはそちらへ移り、河村自動車工業社長の河村二四夫がその代表となる。
一方、清水は、その後「自動車解体部品同友会」から80年(昭和55年)の「HONKONジャパン」を経て、83年(昭和58年)名称を「ビッグウエーブグループ」と変えた組織へ正式に参加した。翌84年(昭和59年)6月、ビッグウエーブグループによって京都で開催された「オールジャパン・ユースドオートパーツ・オークション」は、清水らの「部品交換会」のノウハウが生かされたものであった。89年(平成元年)11月、ビッグウエーブグループは「ビッグウエーブ同友会」に生まれ変わる。清水はビッグウエーブを退会する92年(平成4年)6月まで、ビッグウエーブ同友会の副会長を務めることになる(旧15年史、pp. 56-57)原文のまま。
ここで、改めて旧15年史の巻頭部分を読み直す。
旧15年史は、当時の経産省自動車課長だった保坂伸氏の「設立15年に向けて」の祝辞とともに発刊時に協議会の会長でもあった北口賢二氏のあいさつ文「15年史の発刊にあたって」がある。そこに書かれているのは自動車中古部品流通におきた画期的な技術革命は「ファックスの導入」であったと書かれている(旧15年史、p. 2)。現在でも実は大型の中古部品取引にはファックスが欠かせないと、旧知のトラック解体業者氏が教えてくれたが、ファックスはそれまで競り市に行くか、固定電話であれこれ言いながら部品の性状を説明していた、昭和40年代頃の中古部品商にとっては確かに革新的な技術革命であったのは想像できる。そしてこの技術導入がグループ間での在庫共有システムや部品流通へと繋がっていく。
全国各地に「中古部品流通グループ」が誕生
続いて、清水らのRPCで勉強していた大石一彦らが大分県を中心として立ち上げた西日本グッドパーツグループ(後のNGPグループの前身)が85年(昭和60年)に誕生、追って北海道を中心に86(昭和61年)年に結成されたのが株式会社札幌パーツ社長の工藤洋行を代表とするサッポロ・システム・グループ(SSG)。そして東北地区を基盤としたシステムオートパーツ(SAP)グループが88年(昭和63年)有限会社二興社長、二瓶達夫によって結成されている。また一時期、西日本グッドパーツグループの一員だった北口賢二(株式会社北口車輌社長)は、地域に根ざしたより自由度の高い業者組織を目指して90年(平成2年)に九州部友会(部友会の前身)を立ち上げた。また95年(平成7年)7月には、北九州の有限会社尼岡産業社長尼岡良夫の呼びかけでシーライオンズクラブが結成されている。
山口大学の阿部新准教授(当時一橋大学)によると、日本の自動車解体業のグループは大きく分けて①中古部品の相互流通を目的としたグループ(部品ネットワーク)と、②そのような目的を持っていないグループ(非部品ネットワーク)の2つに整理されるという(阿部 新「解体業者のグループの意義と役割」 所収 竹内啓介監修『自動車リサイクル』東洋経済新報社、2004年)。
(中略)
このように国内の主要な中古部品グループが80年(昭和55年)代の10年の間に誕生している。ひとつの組織が立ち上がると、それを伝え聞いた他の地域の若い業者たちが「それなら俺たちも」と立ち上げた流れに違いない。
当然とはいえ、30年前の若きリーダー達だった彼らが、21世紀の今日、自動車リサイクル部品流通業界でそれぞれ主要な立場にあることは感慨深い(旧15年史、pp. 57-58)原文のまま。
後半は本連載でも多くの研究発表をしている阿部 新山口大学教授が、大学院生時代に書いた分析であるが、非常に的確である。阿部氏の分析に従って設立当時の協議会団体を分別すれば、
部品ネットワークのグループ
株式会社ビッグウェーブ
NGPグループ
SSグループ
システムオートパーツグループ
九州部友会
シーライオンズクラブ
非部品ネットワークのグループ
日本パーツ協会
自動車補修部品研究会
トータルカーリサイクル(TCR)グループ
以上のように分類できよう。
なお、当時のトータルカーリサイクル(TCR)グループは豊田通商によって、1989年(平成元年)に、主として首都圏を中心に組織化されたグループである。そのような事情もあってTCRのTはトヨタのTであるとみられがちだが、当時の酒井清行会長(故人)は「それは違う。確かに、私たちのグループは豊田通商の一営業マン(故人)の強いリーダーシップと、鋭い市況情報の提供によってまとまっていった側面はあるが、自動車から出る廃棄物をできるだけ少なく、たくさんの部品や資源を買ってもらうために集まったグループである、という趣旨の発言をうかがったことがある。TCRグループのウェブサイトを観ても、豊田通商のリードの下、多くの海外視察が実施されている。また、トヨタが愛知県半田市に作ったシュレッダー会社である豊田メタルに安定的に廃車ガラを納めてもらうために、中部地区を中心にできた豊田メタル協力会、大阪のメタル協力会(いずれも解散したと聞く。)とは、豊田メタルへの廃車ガラの供給の有無という意味でもTCRグループは、若干意味合いが違う」。
なお、SSグループに関しては、その後進であるエス・エス・ジーのウェブサイトによると、1986年は「札幌パーツに於いて業界初のCPシステム完成」とあるが、1987年に「正式にエスエスグループとして設立されエス・エス・ジーロゴ制作」と記載されている。http://www.ssg.gr.jp/history/index1987.html 参照
ところで、1990年に顕在化した豊島事件によって、シュレッダーダスト問題が発生し、そのあおりを受けて自動車解体業界でいわゆる逆有償の問題が起こった。廃車ガラをシュレッダー業者に比変わらす際に、処分料をプラスして持って行ってもらわないといけないという2025年8月現在では信じられない時代が35年前には到来していたのである。
このような中で、旧15年史では厚生省(現 環境省)管轄の廃棄物処理法(廃掃法)の改正とともに、通産省(現 経産省)の1991年制定の旧リサイクル法の意義を強調している。
「廃棄」から「再生利用」への転換
改正「廃掃法」では廃棄物処分場の規制強化条項とともに、「廃棄物の排出抑制」と「再生」という考え方がその第1条に盛り込まれることになった。
一方、新たに制定された「再生資源利用促進法」(リサイクル法)は、自動車や大型家電などを対象にし、回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策を新たに講ずることによって3R(リデュース、リユース、リサイクル)の自主的促進が進むことを狙いとしており、特に「再使用(リユース)の概念」が法律上明確にうたわれたものとしては極めて画期的法律といえた。
しかも、自動車は、第1種指定商品として位置づけられており、まさに、中古部品の生産・販売に経営の重点を置こうとしていた解体業者たちにとっては、「業態の持続性の裏づけ」とも云える立法だった。
当時業界では、この法律の略称を「リサイクル法」と呼び、その後、「容器包装リサイクル法」「廃家電リサイクル法」「自動車リサイクル法」「建設資材リサイクル法」など商品別のリサイクル関連法が出るまでは、この表現を使用し続けた。(旧15年史、p. 69)。
これに続いて、当時日刊自動車新聞の記者でもあった永澤氏自らが仕掛けた、初期の業界支援活動が記されている。
新たな法律の裏づけによって、「自動車解体業の社会的信頼性、地位の向上」を狙っていた小田尚、近藤港ら(外川注:前述したビッグウェーグ初期の中枢メンバーで、小田氏は京都、近藤氏は名古屋に拠点持っていた。)は色めき立ったが、この動きに更に新たな応援者が現れた。自動車の専門日刊紙、日刊自動車新聞である。
1929年(昭和4年)に創刊された同紙は、日本に国産車が出現する以前、米国や欧州から自動車を輸入した「輸入車の時代」から「将来、日本にも必ず自動車の時代がやってくる」―との創業者、木村正文の卓見から生まれた新聞であり、まもなく創刊65周年を迎えようとしていた。
日刊自動車新聞は、新車主体の自動車販売店、全国の整備工場を読者基盤とする一方、新たな活動分野として中古車販売業界を支援していたが、当時、話題になりつつあった「環境対策」にも視点を向けていた。自動車メーカーは、まだ試作段階とはいえ電気自動車から水素燃料自動車まで開発を進めており、電気自動車は一部商品化が進んでいた時代だった。そして「再生資源利用促進法(リサイクル法)」に関わる分野は日刊自動車新聞にとっても、新たな読者層拡大先として注目に値するものだった(旧15年史、pp. 69-70)原文のまま。
業界組織を立上げ、「リサイクル・ショー」をやろう
当時、日刊自動車新聞社の新設部門、事業開発室を担当していた永澤卓也は、紙面を通じてビッグウエーブの近藤港の主張と活動に興味を惹かれていた。91年(平成3年)の11月、近藤と永澤の懇談が実現、話し合いは丸一日行われた。この話し合いは、その後の「中古部品流通」の大きな流れを生み出すきっかけとなった。
近藤の立場から見ると、業界密着の媒体である日刊自動車新聞に自分たちの理解者を持つことは、今後の業界組織化活動を進める上で極めて有利になる、と読んだ。永澤は、新聞社の事業開発の責任者として、「業態としては底辺と見られていた中古・再生部品業界へ光を当てる」という近藤氏らの「思い」を、紙面活動を通じて具現化することにより、ひとつの分野の読者層が増えるとともに担当部門である「事業活動展開」のきっかけになる、と考えた。
新たな法律「リサイクル法」(再生資源利用促進法)が両者の計画を実現に導く糸口となったのである。
近藤との会談を踏まえて永澤が行った提案に「オートパーツ・リサイクル協議会結成と記念フェア開催計画」があった。「オートパーツ・リサイクル協議会」とは、近藤らが目指す新たな中古部品流通業者集団と、当時すでに組織化されていた自動車電装品のリビルダーたちによる日本リビルド工業会、ブレーキシューの張替えなどを主力とした足回りリビルダーたちによるリビルド工業会全国連合会、ラジエーターの修理およびストック販売を行っていた全日本ラジエーター工業会を含めた「中古・再生部品関連業界」の幅広い業者同士の連絡・協議機関であり、業界共通の課題・問題点の解決、業界共通の目的達成のための連合組織、と位置づけた。
この「新組織」設立に伴う業界のメリットとして①個別団体を超えた相互の情報交換によって、業界全体の動向が把握でき、商売の拡大など経営戦略に役立つ②自動車業界全体を含めた社会的認知度の高まりによって、850億円程度とされていた市場規模が総体的に拡大する③関連法律およびリサイクル技術などについて監督官庁の指導を一元的に受けることが出来る④自動車解体業界の地位向上によって、構成個々企業のイメージアップにつながる⑤社会的に認知された業態になることにより合理化・環境改善のための公的融資の道が開ける、等が挙げられた。ただし新しい業界組織が出来ることによって、構成する各団体の利益活動が拘束されてはならない、ことの確認も必要、とした。
そして、協議会結成の暁には、その記念事業として、「中古・再生自動車部品の社会的関心と認識を高めるための幅広いPRの場」として、また需要者である全国の整備事業者、中古車販売業者のために設立記念即売会(トレード・フェア)を開催、中古・再生部品の認知と取引拡大を図る、ものとした。
今日の「日本自動車リサイクル部品販売団体協議会」と「オートアフターマーケットショー」のプロトモデル(原型)のシナリオが、このときすでに描かれたのであった(旧15周年史、pp. 70-71)原文のまま。
日刊自動車新聞の「座談会」が契機に
92年(平成3年)4月8日東京ステーションホテルを会場に、組織化活動の前段階として、日刊自動車新聞主催による座談会が企画された。
特別座談会「リサイクル法と再生自動車部品流通の展望」がテーマで、出席者は、中古部品流通業界から株式会社ビッグウエーブ代表の近藤港伏見技研社長、ビッグウエーブ同友会会長の小田尚株式会社太洋商会社長、ビッグウエーブ同友会副会長の樋口隆雄株式会社旭商会社長、同じくビッグウエーブ同友会副会長の清水信夫株式会社清水商会社長。そして病気療養中だった大石一彦NGPグループ会長に代わりNGPグループ副会長の多久島秀敏株式会社多久島自動車社長、同じく副会長の守屋隆之株式会社三森自動車商会社長の6人。
ラジエーター業界から全日本ラジエーター工業会会長の中田達夫中田ラジエーター工業株式会社社長、ブレーキ回りリビルド業界からリビルド工業会全国連合会会長の大庭靖弘日本ウェアハウス株式会社社長、電装リビルド業界から日本リビルド工業会事務局長の新井充晃アライ電機産業株式会社社長の3人。
そして、さらに当時の監督官庁である通商産業省自動車課から長谷川和久課長補佐、沢野弘部品係長の2人が出席した。司会は日刊自動車新聞編集局の間宮潔第3部次長が進めた。
座談会すべてのセッティング、通産省担当官との交渉は永澤が行ったが、あくまでも黒子に徹した。4月8日に開催されたこの座談会は、5月1日付けの日刊自動車新聞に2ページにわたって掲載された(旧15年史、pp. 71-74)原文のまま。
旧15年史には、この座談会の紙面の縮小コピーを、72ページから73ページまで2ページにわたって掲載してある。現在ではメディアで自動車リサイクルや中古部品あるいはリサイクル部品、リビルト部品の記事が定期的に掲載されているが、業界のニーズをいち早くとらえ、それを新聞というメディアで広めたのが他ならぬ日刊自動車新聞社記者時代の永澤氏の功績であった。
自動車解体業界の地位向上によって、構成個々企業のイメージアップ。これは当時の自動車解体業社や、中古部品、リビルト部品を扱う若手の業者には非常に重大な課題であった。そこで、新組織(これが最終的には協議会となるわけである。)の設立に向けた運動が起こる。しかし、この運動はそうは簡単には進まなかった。新組織の設立に関する説明会は、1992年8月から10月にわたって全国7ブロック(北海道、東北、関東、中部、近畿、中四国、九州)で開催された。出席者には特に制限を設けなかった。しかし、近畿ブロック説明会では大きな波乱があった。
【近畿地区説明会開催】
近畿地区の説明会は、9月26日京都市東山区の京都パークホテルで開催され、40社が参加した。本部から近藤港準備委員長、小田尚準備委員、樋口隆雄準備委員が出席。
同地区では、中古部品販売業と解体・スクラップ業が同数、それを上回るリビルト部品販売・修理という構成で、質問の内容もおのずと参加資格基準にウエートがかかった。協議会のめざす方向についても、より幅広いテーマに取り組むべきだ、という提案もなされた。
一部業者と称する人から反対意見が出されたが、それにもかかわらず混乱なく整然と会が進行できたのは、地区準備委員として参加呼びかけに努力した横山和夫株式会社ワールドパーツ社長、多田幸四郎株式会社多田自動車商会社長、市田和久株式会社市田部品社長、林謙治有限会社協進ラジエーター工業社長らの人柄に負うところが大きかった。特に、樋口準備委員の事前の尽力は筆舌に尽くせないものがあったと思われた。
また、司会進行を途中で横山地区準備委員から引き継いだ徳原栄二株式会社近江パーツ社長の水際立った進行によって、波乱含みの緊張した場面もあった近畿地区説明会をしっかりと締めくくることが出来た。
日刊自動車新聞関西支社が取材した(旧15年史、pp.83-84)原文のまま。
さて、以下は旧15年史には掲載されていない幻の原稿であるが、この件は業界史上重要なトピックであるので、その部分を紹介したい。
「自解工」の動きに通産省の態度豹変
この全国説明会が開始された直後から、今まで活動を休眠していた自解工(自動車解体処理工業会)が突然動き始めた。
中部地区説明会が終わった9月10日、自解工の小野順一会長ら5人の幹部が日刊自動車新聞社を訪れ、対応した坂口英夫常務ら新聞社幹部たちに「報道に偏りがある。自解工という組織があるのに、部品リサイクル協議会に大きな紙面を割くのはけしからん」という趣旨の抗議を行った。
小野会長らの発言は①我々は、世間で言われているようにさまざまな経歴を持つ人々で構成されている。昔の関西での事件を知っていると思うが、当時我々が関わっていたのだ②仕事の内容は自動車業界の底辺だが、どんじりとはいえ「自動車工業会と並ぶ5団体のひとつだ」と自負している。廃車問題に関わる会議にも出席し、自動車工業会とも対等に話をしている③最近のお宅の新聞には何かといえば「リサイクル協議会」の記事が派手に出ているが、これは片手落ちというものではないか。我々もリサイクル委員会を発足させているが、こちらの動きは取り上げられず、なんら記事にならない。これは差別ではないか④現在、工業会の会員は1,500社あるが、今日、鉄、非鉄スクラップの価格が極端に悪く、我々のほとんどが部品販売を行っている⑤「AUパーツ」のブランドで市場に出しており、協議会が会員の資格としている「部品売り上げ50%以上」は我々も該当する⑥ビッグウエーブやNGPのメンバーには、昔は我々のメンバーがたくさん居たが、二足のわらじは許さない、ということで辞めてもらった、という内容だったという。
担当だった永澤氏は当事者であるということで、自解工との会談からはずされていた。
当日午後、同件で事務局が通産省に長谷川補佐を訪ねたが、会議のため面会できず。同日夕刻、通産省を再度訪問、説明会の報告を兼ね、補佐とざっくばらんに話し合いした。
その中で長谷川補佐は「業態の末端が、自解工のメンバーと重複しているという実態から、協議会が独自性をどこまで貫けるのか見守りたい、という考えが自動車課内部にある」と通産省への自解工介入の事実を語ると同時に通産省の立場も表明した。
9月17日になり、通産省自動車課から、「近藤準備委員長と至急連絡を取りたい」旨の伝言が入った。
近藤港委員長は、オーストラリアの自動車解体業界団体AARA(Australian Automobile Recycler’s Association)からカンファレンス・展示会「Zoo」への招待を受けビッグウエーブとして訪問団を構成、渡豪中であった。
帰国翌日の22日、近藤委員長は、東京に宿泊、名古屋の自宅にも戻らないまま、通産省に長谷川補佐を訪問した。ここでの長谷川補佐の話は、「自解工の小野会長らの訪問を突然受け、事前の予備知識がなかったため、対応に苦慮した」というものであった。近藤氏にはそうした予感があったが、的中したことになった。
同26日には京都で近畿地区説明会が開催されたが、この時点から自解工による「協議会説明会」への妨害活動が始まることになる。
10月12日、こうした事情のいきさつを知らなかったリビルド関連3団体代表に対し、事務局から「自解工の動向」についての経過説明を行った。本件は、自動車解体業界独自の問題であり、その経緯についてリビルドメーカーの方々が知らなかったことは当然であった。
10月18日午後、日刊自動車新聞の坂口常務のところに小野氏から電話が入った。内容はこうだった。「日刊自動車新聞は相変わらず地区説明会の記事を書いているが煽り過ぎだ」「東京の説明会案内が、うちのメンバーのところにも行っているが、関係はどうなっているのかといった問い合わせが多い」「案内文には<通産省の積極的なご支援を得て->とあるが、通産省に電話をしたところ<まだ回答は出していない>という返事であった。だとすれば<通産省云々>の表現はおかしいではないか」「京都の説明会の案内状が来ていない。出席したいので案内状を送れ」。
その結果は、前述の「説明会の項」で述べた通りとなった(旧15年史に結局掲載されなかった部分を外川とせいび広報社編集部が編集)。
この、「自解工」とは、1956年創立の全国組織でもある自動車中古部品絵流通団体の後継組織だった。実は少なくない自動車中古部品業者もかつてはこの組織に加盟したり、あるいは小野氏たちの動きを認識していた。ただ、小野氏は自動車中古部品流通に関する新しい流れを理解していなかったようで、自分たちが守ってきた組織の存在が脅かされるのを警戒していたのだろう。実際小野氏はこの後も、街宣車を使用して自動車解体業者の苦境を霞が関前で訴えるなどのパフォーマンスをしばしば行った。それは「業界の地位の向上」を命題とする新組織を設立しようとする若手経営者にとっては、非常に頭の痛い存在であったはずだ。日刊自動車新聞では永澤氏の引退後、小野氏の発言や動向も取り上げるなど、多方面からの取材を続けた。なお、小野氏は2022年12月にこの世を去った。その訃報も日刊自動車新聞は報道している(日刊自動車新聞、2022年12月19日号)。
なお、旧15年史では小野氏が会長を務める組織を「自解工」としているが、筆者の調査では当時は1986年創立の日本自動車リサイクル協会の会長であり、この組織はそれまでは全国自動車解体部品協会(自解協、1976年発足)という名前であった。前述した福島の菅野氏が、初めて岡村氏や小田氏、西木氏と出会った場でもある。そしてその組織は旧通産省自動車課の肝いりで、中小企業近代化促進法に基づく業種指定を受けるために組織化したものであった。ゆえに、小野氏の動きを旧通産省自動車課が認識していなかったとは思えない。なお、日本自動車リサイクル協会が「自解工」という組織にいつ改称したのか、あるいは改編したのか、筆者は資料を持ち合わせていない。
さて、このような形で全国7地区での説明会が終了した1992年10月30日当日、準備委員会が召集され、同日午前、会議の前にそろって通産省を訪問し、説明会の終了報告を行うとともに、今後の組織化の支援についても改めて要請した。
しかし、対応した通産省自動車課の課長補佐からは「協議会の趣旨は理解している。しかし、業界末端では自解工と重複する部分もあり、これについて自解工側からクレームがついている。両者の棲み分けが出来るかどうかにかかっており、通産省としては、この状態解決まで、組織化問題は当分静観したい」という回答が返ってきてしまう。
通産省の対応は「自解工」問題で豹変?したが、一方、協議会の活動を促進させるために準備委員の拡大を計画、新たなメンバーが加わった。
その日新たに準備委員として加わったのは新任の斎藤貢NGPグループ会長(三重パーツ代表)、中山栄リビルド工業会全国連合会副会長(中山ライニング工業代表)、羽田正日本リビルト工業会副代表(HSストロング社代表)の3氏。紹介と挨拶の後、大庭靖弘委員から「リビルト業界としては業界の新しい動きをみてもらおうと、東京の説明会に部品卸商社を呼んだが、結果は残念なものとなってしまった」などの発言が行われ、これをめぐって議論がなされた。
小田尚委員から「通産省とは、今後とも接触を続け、理解を深めるための努力は続けたい」との発言があり、また近藤港委員長からは「協議会の設立準備については、客観情勢を十分に踏まえながら、テンポを落として慎重に進めて行きたい。将来を踏まえ、当方としては、通産との関係を保って行く」との見解が表明され、委員も了承した。
(中略)
また今後の日程については、93年1月下旬に準備委員会を開催、地方拡大委員の選出を行う②これに基づき、3月17日に拡大準備委員会を開催、会議終了後に、設立活動とは切り離して、計画が進められている「第1回オートリサイクル・テクノロジー(ART)ショー」を視察する③設立総会は93年度に入ってからとする④名称変更も議題としたが今回は見送る⑤問い合わせについては事務局が従来どおり対応する、とした。
協議会の設立日程を延期した結果、「第1回オートリサイクル・テクノロジー・ショー93」について、協議会は主催者の立場になりえないが、準備委員会の構成団体が個別に参加支援して行くことを申し合わせた(旧15年史、pp. 86-87)。
このように協議会が発足する前に、既存業界との関係整理が通産省から指摘されるようになったが、実はこのような形態は現在でも日本自動車リサイクル機構と、本稿で扱っている協議会が両党迭立のような形で併存している。このことについては別途検討したい。
(次回に続く。)
参考文献
日本自動車リサイクル部品販売団体協議会編(2010)「『リサイクル部品』とともに15年 日本自動車リサイクル部品販売団体協議会15年史」日本自動車リサイクル部品販売団体協議会。