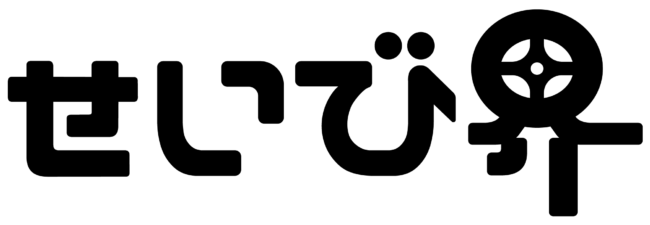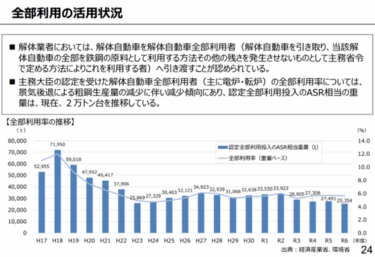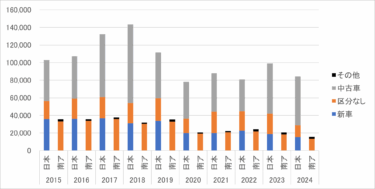熊本大学大学院人文社会科学研究部(法学系)・環境安全センター長
外川 健一
1.はじめに
前号(自動車リサイクルの潮流第173回)に引き続き、旧協議会15周年史を読み進めていこう。前回は1992年代の協議会設立運動が挫折したところまでを振り返った。
その後、シュレッダー業者でもあり、自動車解体に熟知している富山の豊富産業の高倉康氏社長、大阪の株式会社伸生(現 伸生スクラップ)の多屋貞男社長である。
2.不思議な邂逅と新たな展開
1993年11月20日、福島県の解体業(有)富山商会の白川広社長の紹介で、富山県の「自解工メンバー」だという解体工場から事務局(外川補足:旧協議会設立準備のための事務局、実際には永澤氏が切り盛りしていた。)に電話が入った。聞いてみると、「協議会に入りたいと考えているが詳しい話しを聞きたい」というものだった。現地確認を兼ね富山県を訪れて驚いた。「いわゆる解体業」をはるかに超えた大規模な廃車処理工場だった。富山県には数社あるシュレッダー会社のひとつ、豊富産業株式会社である。電話の主は、代表取締役社長(当時)を勤める高倉可明氏だった。
高倉社長は研究熱心で、廃タイヤを蒸し焼きにして発生するガスを回収、これを燃料としてアルミエンジンを原料としたアルミ溶融炉を稼動させる実証実験に取り組んでいた。回収した廃車の中には、再使用が不可能なエンジンもあるためで、すべて廃棄物だけで再生産が可能なシステムだった。しかも、その余熱を使ったボイラーから近所の農家にパイプで温水を供給。冬期でもビニールハウスによる野菜の成育が可能になっているという。
高倉社長は自解工へ加入したときの状況、その後の活動、自分たちが目指している業界展望などを熱く語ってくれた。事務局からは今までの協議会設立の経過、出来事をすべて話した。
同社は、エンジン用アルミインゴットを自動車メーカーに収める一方、金属スクラップの輸出貿易も幅広く行っているなど営業の規模が大きく、協議会のメンバーが中小自動車解体業であるところから、同社が目指している組織とは若干異なると判断したのか、報告は聞いてくれたが、その場での加入の即答はなかった。
高倉社長との会話がはずみ、その中で、当時、自民党最大派閥の宮澤派に属し自民党幹事長代理をしていた加藤紘一衆議院議員の後援会長をしている、とも語ってくれた。加藤幹事長代理は後に自民党幹事長となり、山崎拓・小泉純一郎両衆議院議員とともに当時の若手政治家のホープ「Y・K・K」として注目を浴びることになる。高倉社長とのこの不思議な出会いが、後で大きな問題を解決することにつながる、とは当時想像もできなかった。
3.「第1回リサイクルショー」で揺れる通産後援
1993年(平成5年)2月、協議会事務局を兼ねる永澤は3月開催の「オートリサイクル・テクノロジー・ショー93」の準備に追われていた。ショーの後援を依頼していた運輸省、環境庁からは決定通知が届いた。だが通産省からは返事が無かった。8日になって、通産省担当官から「後援は困難」との情報が入ってきた。「大臣官房が業界紙である自動車新聞社の後援はできないと反対している」ということだった。おそらく(中略)、「触らぬ神にたたりなし」とでも思ったか、担当窓口が積極的なアプローチを渋った可能性が考えられた。ショーの担当である永澤の責任だ。
このときひらめいたのが、昨年の暮れに会った富山県の高倉社長との対話のことだった。最初の面談のときにも、「オートリサイクル・テクノロジー・ショー」のことは案内済みであり、同社の「廃タイヤ燃焼余熱の農家への多目的利用」活動は、ショー併設の環境セミナーには絶好のテーマだと、セミナー講師に高倉社長を推薦し終わったところだった。早速、親展の手紙を高倉社長宛に送り出し、追っかけ電話でも事の顛末を伝え、支援をお願いした。「たった一度の面談者に」である。
当時の行政の慣行として、各省の大臣に次ぐ次官は最低2名おり、一人は官僚からの事務次官、一人は政治家が就任する政務次官と呼ばれた。政治家が就任する政務次官の方が格が上だった。当時の通産政務次官逢澤一郎氏(岡山県第1区選出代議士)は同じ宮澤派に属し、加藤幹事長代理とは仲がよかったという。
19日になって、通産省の担当官から突然「後援承認」の連絡が入った。高倉社長が加藤自民党幹事長代理に働きかけをしてくれたことは確実だった。「政治的圧力がかけられた」として通産省から事務局に執拗な問い合わせがあったが、真相を話すことは絶対出来ない相談だった。
その後、通産省の協議会関係者に対する対応が、今までとは変わったように感じられた。「人の絆(きずな)」の大切さを改めて思い知らされた事件であった(旧15周年史、pp.87-88)。
高倉氏は、21世紀における日本の自動車リサイクルのイノベーションになくてはならない機械の開発にも一役買っている。それは、氏がアイディアを出しながら株式会社コベルコ建機と一緒に開発したマルチ自動車解体機である。これは俗にいわれている重機(ニブラ)を自動車解体専用に設計したもので、それまで手作業で行ってきた解体ではできなかった車内に点在するワイヤーハーネスやモーターコアといった銅分の多い資源性の高い部品の回収を、この機械の導入によりスピーディにできるようになった。つまり、これらを手作業で取り出すには多くの時間がかかったが、ニブラ重機を使えば、力強さと精密さを活かして効率よく回収できるようになった。この自動解体機の1つのポイントは、解体する自動車をしっかり押さえる部位や、掴んだりする繊細な作業もできるアームの開発であった。これらは高倉氏のアイディアが大いに使われたという。
一方、協議会にとって大きな出会いは、日本で初めてシュレッダーを導入した会社の1つであり、自動車中古部品も古くから取り扱っていた、株式会社伸生の多屋貞男社長との出会いである。多屋氏は一橋大学を卒業後、ドイツで選鉱分野の学問を学び、日産自動車で働いていたこともある理論派で、資源工学系の学会や海外でのリサイクル業界団体のカンファレンスにしばしば顔を出していた。本連載でお馴染みの阿部新山口大教授ほか、自動車リサイクル研究を行っている一橋大学出身者グループは、研究を始めるにあたってこの多屋氏や東京海上から、株式会社自研センターに移った竹内啓介氏が現場の紹介などの手助けしてくれたと聞いている。なお、多屋氏はその後、自動車補修部品研究会の正会員となり、業界のオピニオンリーダーの1人となっていく。
4.株式会社伸生の多屋社長からの進言
この間、協議会の活動計画は、徐々に業界に浸透しつつあった。損害保険協会から、また損害保険業界と関連の深い株式会社自研センターからの問い合わせがある一方、(中略)関西の大手自動車処理業、(株)伸生の多屋貞夫社長から、「オートARAリサイクル・ショーをやるなら米国の自動車解体業協会(Automobile Dismantlers and Recyclers Association =ADRA)の代表にも案内を出してはどうか」との提言をもらった。氏は当時唯一のADRA日本人会員だった。
今まで国内の足元だけを見ていた活動だっただけに、多屋社長からの進言に目からうろこの思いで即実行に移した。ADRAのスタインクラー(W.Steinkuller)副会長兼専務理事とコンタクトが取れたのは幸いだった(旧15周年史、p. 88)。
なお、ADRA はその後、ARA:Automotive Recyclers Association と改名し、1943年の設立以来、活動を続けている。(ARAのウェブサイト:https://www.a-r-a.org/ 参照。)さて、この多屋氏のアドバイスを受けて、自動車リサイクルショーを自動車リサイクルを国内問題ではなく、国際的な共通の課題としてアピールした点が興味深い。以下、再び15年史を読み直してみよう。
「環境と自動車リサイクル」をテーマとした第1回国際自動車リサイクル・テクノロジーショーは、1993年3月17日に開催された。アメリカの業界団体でもあるADRAの参加もあり、また「自解工」からの参加も受け付けた結果、通産省もこのオートリサイクル・ショーに、メーカー団体の自工会とともに参加した。このショーではビッグウェーブの近藤港氏が国内情勢を話すと同時に、伸生の多屋社長が海外と日本の自動車リサイクル事情と課題の比較」を講演した。ADRAのビーゲル会長の、自動車リサイクル先進国アメリカの事情の講演があったのも非常に意味があった。
さて、自動車中古部品を扱う業界団体の全国組織の設立はいったんとん挫したが、通産省自動車課の人事異動を契機に、再度全国組織をつくろうという動きが加速する。具体的には、通産省自動車課の担当が竹中速雄課長補佐(企業・流通班長)、戒能一成課長補佐(技術・部品班長)に交代した。これが実は大きな契機となる。とくに戒能氏は自動車解体・リサイクル業界の事情を良く研究し、1995年に業界の指針を与える講演を行ったからである。
5.業界の「バイブル」となった戒能講演 反響読んだ「第1回リサイクル部品フォーラム」
阪神大震災で始まった1995年(平成7年)は、国内の政治情勢の不安定さと急激な円高の中で経済の閉塞感にさいなまれていた年でもあった。
1993年(平成5年)8月、自民党の宮澤喜一内閣が倒れた後は、非自民の細川護煕内閣が94年(平成6年)4月まで、同じく非自民の羽田孜内閣はわずか2ヶ月で非自民の村山富一内閣へバトンタッチ、1996年(平成8年)1月まで合計3年間弱で首班が3回変わる異常政局であり、円相場も1ドル80円という輸出にかかわる業者等にとっては最悪の水準であった。
だが、自動車リサイクル部品流通業界にとっては、過去との時代の流れを画する、まさに画期的な年となった。
それは、新たな活動のために開いた「部品フォーラム」での通産省自動車課の戒能一成課長補佐の講演が、参加者にとって大きな「勇気と展望」を与える内容だったからである。講演は、予想外の衝撃と反響を呼んだ。
1995年3月14日、名古屋市内の都ホテルを会場に(株)ビッグウエーブ(近藤港社長)主催の「第1回自動車リサイクル部品フォーラムin名古屋」が開催された。前半は「リサイクル部品業界の地位確立」などを主題にしたリサイクル部品流通団体代表による討論会。後半は、通産省から戒能一成自動車課課長補佐を講師に招き、講演会を開催するスケジュールであった。
(中略)
引き続いて、通産省自動車課の戒能一成課長補佐による記念講演が「自動車部品再生・再利用に関わる課題と展望」と題して約1時間にわたって行われた。
講演では、フォーラム前段で討論された「業界が抱えている課題、将来に向けての問題点」について明快・的確に指摘が行われ、参加者に大きな感銘を与えた。
業界にとって非常に幸運だったことは、講師に招いた戒能課長補佐が、技術・部品班長を兼任し、新車の組付けから補修市場向け部品にいたる製造・流通はもちろん、リサイクル部品の将来についても極めて明確な知識と展望を持っていたことだった。東京大学工学部資源開発工学科を優秀な成績で卒業(1987年)したと同時に通産省入省。資源エネルギー庁勤務を経て本省機械情報産業局の自動車課課長補佐就任という工学系キャリアである。
6.リサイクル部品業界の生き残り策を説く
戒能補佐は、講演の中で、「リサイクル部品」という言葉を使い、業者たちを「リサイクル部品業」と明確に呼んだ。
そして「リサイクル部品」が社会的信頼を獲得するための必須条件として①供給の安定性②品質の信頼性③価格構造の透明性、の三つの重要性を指摘した。
また、「解体業」と「部品流通業」とは別のもの、と言い切り、二つの部門を分離しておくことによって、「ビジネスチャンスの機会損失」を未然に防ぐことが出来る、と強調した。この指摘は、親子代々からの「解体業」だったという参加者たちにとっては前代未聞の話だった。
[供給の安定性]については、「最上の社会的信頼の醸成基盤は『実績を示すこと』に尽きる」と表現した。そして、その手段として「同業者が連携して流通ネットワーク化していくしかリサイクル部品業界が生き残れる道はない」と言い切っている。
[品質の信頼性]については、「信頼性のないものは、それなりの市場しか獲得できない」と断言。リサイクル部品だからこそ、供給側がきちんと検査したものを供給する形としなければ、大きな市場形成は困難、と指摘した。また、こうした検査を地域の解体業者に期待しても無理があり、リサイクル部品流通業者として専門訓練を通じての熟練と検査設備が必須だ、と説いた。
そして具体的には①自己検査・評価体制の確立・標準化が必要②外装部品については「仕入れ仕様の許容限度の明確化」が必要である。すなわち仕入れ工程で、品質を担保しようとすることは今後とも期待できない③機能部品については「検査仕様の明確化」が必要、であることを明言した。
[価格構造の透明性]については、「納得される価格でないと新品とは競争できない」と指摘。ユーザーに受け入れられるかどうかは品質と価格のマッチングであり、在庫についても公表が望ましい、とも指摘した。
そして最後に「部品メーカーは、長い目で見てこの市場に進出してくるだろう。こうした動きにいつ来てもよい立場にするために、リサイクル部品業界としては、早急に組織化をする必要がある。指摘した3つの点に留意し、熱心に取組んで行く団体に行政は積極的に支援していきたい」と締めくくった(旧15周年史、pp. 100-102)。
ここに、現在へと続くリサイクル部品業界団体は、「中古部品」ではない、「リサイクル部品」という差別化とビジネスチャンスの道を見出した。筆者はこのアイディアが戒能氏独自のものかどうかは知らないが、通産省の熱心な若い役人が成長しそうな業界をとことん調べ上げ、その成長戦略を示唆することは大いに考えられる。そして①供給の安定性、②品質の信頼性、③価格構造の透明性、の中でも特に①の問題解消のため、リ協メンバーは今年から本格的にARPNをスタートさせたのだと思う。そして、このシステムによるリサイクル部品の商流の拡大は、②品質の信頼性、③価格構造の透明性へと繋がるポテンシャルがある。なぜなら、品質の信頼性がなければ既存のブロードリーフやヤフオクへと業者もユーザーも流れるわけであるし、価格構造の透明性に関してもその問題が解決されなければ中古車のレモン市場のような状態に陥ってしまうからである。
なおレモン市場とは、売り手(この場合リサイクル部品の販売業者)と買い手(この場合、整備業者などリサイクル部品を求めているユーザー)の間で商品(リサイクル部品)の品質に関する情報に大きな差(経済学ではこれを「情報の非対称」と呼ぶ。)があるために、低品質な商品ばかりが流通し、高品質な商品(これが「リサイクル部品」であり、いわゆる補償等がない「解体部品」と差別化している)が市場から駆逐されてしまう経済現象のことである。
7.供給の安定性を求めて-在庫管理システムから在庫共有ネットワークへ
1995年はウィンドウズ95の販売年であり、これを機に爆発的にパソコンが身近な道具として市民全般に広がっていく。
実は、コンピュータでの部品流通の時代が来るといち早く悟った先人たちがいた。旧15周年史第6章によると、その先端を走っていたのはRPC(リビルトパーツクラブ)のメンバーであり、ビッグウエーブ同友会のメンバーであった。
RPCのメンバー(株)清水商会の専務取締役だった清水信夫の話によると、『中古・再生部品の在庫交換会』が目的で結成されたRPCだが、基本になるのは自社在庫管理からで、はじめは「社内の誰でもが電話を受けながら見られる」ということでホワイトボードに線を入れたものを2枚用意した。これに手持ちの在庫部品を書き込んでゆく。在庫量が増えると、それでは間に合わないというので、着目したのがコンピュータ。
当時小型のオフィスコンピュータが三菱電機を筆頭に出まわってきた時期で、清水商会で導入したのが日立製のオフコン「HITAC」3台。1台は本社に置き、2台は2人の担当社員の自宅にそれぞれ持ち込み、自宅でその日の生産品を在庫登録をした。今では見られない「磁気テープ式タイプ」で、データ入力したそのテープリールを本社のコンピュータにかけ、在庫一覧をプリントして、それで商売をしたという。今では当たり前の風景だが、社員が5、6人しかいなかった時代に、社員の給与の数年分に相当するオフィスコンピュータを使いこなしたという清水商会の先端ぶりだった。1980年代(昭和55年以降)後半はオフィスコンピュータの国産化が進んだ時代で、清水商会の成功を聞き込んだ同業者が、足繁く見学に訪れたと言う。
8.ネットワーク構築はビッグウエーブが最初
株式会社ビッグウエーブの会社案内「3WAVES」によれば、ビッグウエーブは1985年(昭和60年)12月に、NTTデータ通信(当時の日本電信電話公社子会社)と組みVAN(付加価値通信網)システムによるコンピュータのネットワーク「BIG ネッツ(NETS)」を最初に構築している。会員企業が生産、保有するリサイクル在庫部品をデータとしてコンピュータに登録、これを会員同士が検索、引き当てして売買するネットワークシステムである。
これは、加盟会員がすでに個々レベルでコンピュータを導入、使いこなしていたことを意味する。96年(平成8年)にはほとんどのビッグウエーブ会員はコンピュータと共にG4と呼ばれる最高速の機種のFAXも使っていた。
もともとリサイクル部品流通業は、販売業者である以前に生産者である。使用済自動車なり事故車なり、いわゆる「部品取り車両」から再使用可能な部品を見極め、車体から取り外す工程を「生産」と呼び、「中古部品を生産して販売」するメーカーベンダー(Makervender(ママ))だ。取り扱う部品の特色は一点ごとの履歴が異なるわけで、厳密には「同じ部品」はひとつもない。部品取りのための入庫車両の一台一台がメーカー、年式、走行距離数が異なるためで、それらの在庫管理は従来の台帳による管理では当然限界がある。
前述した清水商会がそうであったように、いち早く導入されたのがコンピュータによる管理であった。しかも、全国ネットであるためデータとして「大量・多品種在庫」が可能になると共に、在庫情報が全国にスピーディーに流れ、無駄な在庫(休眠在庫)が大幅に減少することになった。(15周年史、pp. 158-159)。
筆者はトラック部品に特化した、業界随一の流通ネットワークJTPの創立前後の2001年から2002年にかけて、何度かこのトラックリサイクル部品の在庫旧友ネットワークの創設者であり、ビッグウェーブの創立メンバーでもある奥野松方氏にインタビューをさせていただいた。そして、1985年のビッグネッツの設立には奥野氏が、氏の地元である金沢市のNTTを通じて、NTT関係の技術者と何度も情報交換し、システムの開発に携わったという話を聞いた。とにかく自社在庫管理だけではなく、ビッグウェーブ全体の在庫部品を、ファックスで問い合わせるのではなく、いつでも見られるコンピュータで繋げ、ユーザーの需要にいち早く応えていきたいというシステムの必要性を当時の若手経営者は野生の勘で感じていたのであろう。ただ、トラック部品の流通に関してはどうしてもFAXでのやり取りが必要なことが多かったという。それは2025年の現在でも同様であるようだ。
9.グループ内だけが利用できる在庫システム
リサイクル部品協議会設立時(95年(平成7年))のビッグウエーブ会員は57社であったが、ほぼ全国に点在、いずれも地域に根ざした大手解体業者であり、経営基盤もしっかりしていたこともあり、ネットワーク流通システム「BIGネッツ」構築も早かった。
その後を追って組織化を行ったのがNGPグループであった。NGPグループは、組織化が二番手であったこともあり、ビッグウエーブを目標に「追いつけ追い越せ」のスローガンを掲げて、会員数を拡大させ、コンピューターソフト開発についても、会員が要望を出し合い「理想とするシステムづくり」を目指した。「スーパーライン」と呼称するシステムである。
その後、更に組織化が行われたシステムオートパーツにしても、九州部友会、シーライオンズクラブ、SSグループにしても、新しいグループの誕生とともに、グループ独自のシステム開発をめざした。
このように、「新たな流通団体が誕生するごとに、新たなシステムも作られる」ことになったのだ。
当時は、インターネット利用ではなく「NTT専用回線の利用」という通信方式で、安定した通信は確保できるが、あくまでも会員専用で、会員以外は使えないクローズド方式であった。そのため会員数が多いところはソフト開発費の分担分も少なくてすんだが、会員数の少ない組織は、ソフト開発費の負担分が経営の負担となった。しかも「システムの所有権は組織会員ではなく、ソフト開発会社が握る」という状況下にあった。
まず先行したビッグウェーブのシステムに対抗して、後発のNGPは創業者の大石氏が別府信用金庫の協力を得て、ビー・ビー・エフによるスーパーラインシステムを構築する。大石氏はまず九州を中心に同志を募り、90年代前半には一大勢力となった。その一方でNGPの経営理念に同調できない人々がこの組織から脱退し、それぞれのシステムを持つようになる。九州部友会、シーライオンズクラブがその例である。
一方、東北地方の有志が集まってできたシステムオートパーツ、北海道の札幌地方が中心でできたSSグループなどは独自のシステムを開発して、地域内でのリサイクル部品の流通を進めていった。
10.協議会の設立(1995年11月)
このように群雄割拠するたくさんのシステムは、1995年に販売されたウィンドウズ95の影響が大きいことを改めて強調したい。このOSの登場で、かなりのシステム業者と自動車リサイクル部品在庫流通ネットワークが接近し、それぞれのグループの需要に応じたシステムが従来に比べ低コストで簡単に作れるようになったのである。理想からいえば、新たな業界団体の下で、加盟団体共通の「ネットワークシステム」が構築されれば、加盟会員全体の在庫部品がお互いに利用し合えることが可能になり、部品流通も大きく促進されることになる。またコスト的にも各団体の負担が軽減されることが予想された。
このような動きの中、ようやく協議会は設立された。1995年11月のことである。
95年(平成7年)11月28日の設立総会は、第1部の記念講演会から始まった。講師は通商産業省機械情報産業局自動車課の渡邊昇治課長補佐と、株式会社自研センター代表取締役の竹内啓介所長のお二人である。
渡邊補佐は、戒能一成補佐の後任として、1990年通産省入省、工業技術院、資源エネルギー庁を歴任後、本省機械情報産業局自動車課に着任した。偶然というべきか、渡邊も戒能も東京大学工学部を卒業、通産省に入省している。二人の共通項はいずれも「役人らしからぬ役人」であったことだ。
戒能は、名古屋で開催された「自動車リサイクルフォーラム in 名古屋」での講演でも明らかなように、極めて論理的に自動車リサイクル業界を展望していた。一方の渡邊は、機械工学を学び、自らドライバーとして突っ走り、エンジンの調子も自分で調整してしまうという技術屋趣味人としての感覚を兼ね備え、実践的にこの業界を理解しているというタイプのように見受けられた。
竹内啓介社長は一橋大学経済学部を卒業、東京海上火災保険に入社。ニューヨーク支店長、常務取締役大阪支店長を経て、損害保険業界のための「保険料支払いに伴う修理費指数の研究機関」(株)自研センター代表取締役に就任している。氏のセンター代表在任中における世界自研センター会議(RCAR)への出席報告書は、国内の自動車整備業界・リサイクル部品業界にとって、世界の動向を知る上での大きな情報提供の役割を果たした。
渡邊補佐は、「自動車リサイクル部品産業の課題と動向」と題した講演で、厳しい国内経済状況を反映し、国内での自動車の伸び悩みとともに自動車部品産業も低迷を続けており、補修部品市場については、車検制度の緩和、部品の長寿命化等の影響により市場が縮退する傾向もあるが、一方でオートブレーキコントロールシステムやエアバッグなどの安全装備の進展、ナビゲーションシステムの普及など活性化が見られる部門もある、と分析。また資源の有効活用、車検の低コスト化等の観点から、リサイクル部品の流通の増加に期待感がある、と指摘した。
また自動車リサイクル問題については、年間500万台も発生する廃自動車の処理は、社会的に大きな問題と認識。ことに廃自動車から発生するシュレッダーダストの減容化の方策が必要と指摘。シュレッダーダストを減容・固化する等の技術開発や自動車の設計段階からのリサイクル性、解体性を考慮する等の対策も有効だが、中古部品のリサイクル促進も有効な手段だと考えると指摘。
リサイクル部品が抱える問題、については①PL法(製造物責任法)の影響等により、日本ではリサイクル部品の使用に抵抗感があるように見受けられる。ただし米国ではPL法があるからこそ安心してリサイクル部品を使用できるという説もある②日本の場合、自動車は中古販売が伸びており、部品に関してもリサイクル部品に対する抵抗感は減るのではないか、という見方がある③いずれにせよ重要なのはリサイクル部品の信頼性を保証し、消費者の信用を得ること④そのためには規格や試験方法の整備が必要⑤また中小企業性が高い日本のリサイクル部品産業が、大資本との共存共栄をうまく図っていけるか否かも重要⑥業界の組織化、高度化がカギといえる、と締めくくった。
自研センターの竹内社長は「日本の自動車損害保険、海外の自動車損害保険事情」と題して講演した。
渡邊氏はこの後、1997年に使用済自動車リサイクルイニシアティブを作り上げるのに一役買い、自動車リサイクル法に向けた素地をつくっていく。また、竹内氏は損保業界の立場から、業界にこの後大きな影響を与える。なお、「せいび広報社」で、自動車リサイクルに関する連載が、当時竹内氏の母校でもある一橋大学の大学院生だったメンバー(ちなみに阿部新教授もその一人である。)に書く機会を与えられたのも、竹内氏の口添えがあったからである。
この設立総会には、来賓として首相を退任して1年半を経た日本新党(当時)の細川護熙衆議院議員が参加したのも、参加者の注目を浴びた。細川氏を呼んだのは熊本県のとある破砕業兼解体業者の口添えがあった。
そして会長には2大勢力のビッグウェーブや、NGPからではなく、九州部友会(現部友会)の北口賢二氏が選出された。以下、設立総会での北口氏の挨拶である。
「ご承知の通り、今日、私どもの関わる自動車産業をはじめ、経済産業活動の発展とともに、生活の快適さ、便利さを享受できるようになりました。しかし、その反面、排気ガス等に伴う地球の温暖化、またフロンガスによるオゾン層の破壊、酸性雨、そして大量の廃棄物の問題と、かけがえのない地球の環境問題が大きくクローズアップされるとともに、環境負荷を少なくするための省資源、省エネルギー活動への積極的な取組みが求められるところとなりました。」
「91年、再生資源の利用の促進に関わる法律、いわゆるリサイクル法が施行され、特に自動車は、第一種の指定製品として指定を受け、自動車リサイクル活動への法的根拠と、これに伴いリサイクル部品流通業務への弾みがついたものと受け止めております。」
「自動車は、早くから再利用されてきた商品ではありますが、こうした機会に、まず私ども自動車リサイクル部品の業に携わるものが、率先して、再利用率の向上、幅広いユーザーへの普及活動に取り組むべきであると考えます。」
「私たちは、社会に安心して受け入れられる業態作りをめざすために、数年来、業界の統合化、組織化活動に取り組んでまいりました。本日ここに日本自動車リサイクル部品販売団体協議会が発足いたしましたのも、このような背景によるものであります。」
「当協議会は、現在業界内の9団体で構成された連合組織で会員企業数は約340社となります。すでに独自のコンピューター・ネットワークを持ち、また商品の品質管理につきましてもグループ内のものではありますが、一定の基準に従い、商品化と出荷に際しての保証を行ってきております。しかし、それは業界全体の決めとはなっておりません。当協議会の使命は、業界外の皆様、ユーザーから見ても、これは質が高い、安心して使うことが出来る、というお言葉がいただけるような、業界共通の品質基準や統一保証制度を早く発足させることにあると思います。」
「当協議会は、とりあえず中古部品の取り扱いメンバーを中心にスタートするわけですが、今後、リビルト部品業などの関連団体とも連携を強化し、我々とともに活動していただけるよう期待申し上げるところでございます。」
「欧米では、すでに、このような組織が結成されており、官民一体となって、活動に取り組んでいると聞き及んでおります。わが国でも、やっと懸案の協議会が発足しました。これを機会に通商産業省はじめ、関連業界団体のご支援とご協力を戴きながら、リサイクル部品の活用普及の促進、高品質、迅速・安定した供給体制の基盤作りにまい進、努力いたす所存でございます。」(旧15年史、pp. 128-129)
私事であるが、九州在住の筆者はこの北口賢二氏にどれだけ研究上お世話になったかわからない。とくに2000年から2002年には、沖縄や奄美の不法投棄現場を一緒に観ていただき、業者の目でこの惨状の原因を解説してくださった。また、九州経産局の調査でタイに行くときにご同行いただき、バイクだけではなく四輪でも急成長するこの地のリサイクルの現場を一緒に調査していただいた。さらに氏が会長を務める部友会のメンバーの方々を紹介していただき、自動車リサイクルの現場を観るきっかけを作っていただいた。
しかし、北口氏もこの9月に帰らぬ人となった。この6月に2人で熊本市内のレストランで食事をとりながら昔話をしたのが最期だった。北口氏には心からの感謝を記すとともに、ご冥福をお祈りしたい。
11.ARPN構想は90年代、協議会設立前から始まっていた
ビッグウェーブはNTTのシステムであるハイパービッグネッツを、NGPはスーパーラインを、またそれぞれのグループが各々でリサイクル部品の在庫共有ネットワークを持っている。これを1つにすれば、お互いがウィンウィンになるはずだ。ARPNの原型「A-JAPAN構想」は協議会設立当初から中心となる検討課題となった。この点を旧15年史で確かめてみよう。
「A-JAPAN」いち早く名乗り
こうした中、リサイクル部品協議会の第2回準備理事会で「協議会規約」の審議を終えたばかりの95年(平成7年)8月、工藤洋行準備理事(SSG会長)から事務局に長文の案内書が送られてきた。
「コンピューター利用グループの全国統合的な組織はできないものか」-仮称オールジャパン・ユースドパーツネット、いわゆる「A-JAPAN」構想である。提案者である工藤準備理事は、(株)ビッグウエーブの副社長を兼務、SSG(サッポロ・システム・グループ)会長、(株)札幌パーツ代表取締役社長であり、ネットワークについて熱心だった。
当時の工藤準備理事からの「提案の動機」を語る案内書の一文を披露する。
「(95年)3月14日行われたリサイクルフォーラム in 名古屋において行政サイドより出席戴いた通産省の戒能氏の講演にもありますように、今後大手資本等の参入も考えられる状況の中で、リサイクル部品の安定供給を図るには販売とそれぞれの要求を補完する、情報センターシステム(業界による統一的、互換性のある商品情報システム)を構築し、総合流通により、経営規模の零細性を補足しあってビジネス機会の拡大を図り、市場の不安定性とリスクの増大を解消していく必要があります」
「既に、個々の単位或いは一部のグループ同士により、人的、物的交流が図られておりますが、もう少しそれを拡大しコンピューターを利用した組織的なネットワークが構築できないものかと日頃考えておりましたが、先般自動車リサイクル部品の全国組織が旗揚げされ、そこにおいて品質、価格、保証といった事柄を統一的に考えることが可能となった今、それらを基本に置いて流通にターゲットを絞り込んだ流通上のすべての問題を専門的に考える組織があっても良いのではないか、ということで、あえて片田舎より口火を切らしていただきました」(原文)
その上で、
①コンピューター利用グループの全国統合的な組織はできないものか
*オールジャパン・ユースドパーツネット(A-JAPAN)
②ホストコンピューターを共有できないものか
*大型コンピューターをアウトソーシングで運用
③同一ソフト及びOSを使用できないものか
*新システムを共同開発することにより廉価となる
④同一端末または互換機を使用できないものか
*共同購入のメリット
<上記が少しでも可能性があるならば>
⑤現行の状態でネットワークを組んだ場合、最低どこまで統一化したシステムにするのか?
*現行システムより新システムへのコンバージョンは出来るのか
⑥現行のシステムサポート会社の役割分担は?
⑦ホストコンピューターへのアクセス方法は?
⑧A-JAPANの運用形態はどうするのか?
と構想に伴う問題提起もしている。この考え方は、協議会の設立時の活動計画のひとつであり、また具体化するとすれば乗り越えねばならない課題でもあった。
この呼びかけはNGPグループ、ビッグウエーブ、SAP、九州部友会の代表、システム担当役員、システムサポート会社の代表に限って行われた。この呼びかけに4団体の代表者が全員参加した。九州部友会は北口賢二会長、森孝一システム委員長、A&G社の小西伸博課長、NGPグループは矢田充会長と(株)スーパーライン社の斉藤貢社長の2名。(株)ビッグウエーブは近藤港社長、田中晋次常務、(株)スーパーテック社の川口広武社長、SAPグループは、二瓶達夫本部長、森下秀次システム委員長、(株)岩手コンピューターの浅井透社長、そしてSSGからは工藤洋行会長、鶴岡敏雄副会長、サンクレエ社の宇野博人社長が出席した。
会合は8月30日午前11時から東京港区の都イン東京で開催された。
ここで正式に「業界統合オープンネットワーク化への参考試案」としてオールジャパン・ユーパーツネット構想が提示された。
構想には、構築へのポイントとして①各組織、各企業の独立性、自主性を尊重した形でのオープンネットワークの構築②価格競争等への動きに歯止めをかけ、健全な業界作りに結びつけることが出来るネットワーク化③共同、融合することにより、業界としての市場拡大を図ることが出来るネットワーク化④顧客からの安心感、信頼度を向上し、大手資本参入等に業界として的確に対応できるネットワーク化、を挙げた。そして具体的なネットワークの形態として①分散ホスト直接接続ネットワーク型②統合ホストによる分散ホスト接続ネットワーク型③その複合型の3形態を提案、統合ホスト方式の場合はホストコンピューター運用のための新会社設立も行われる予定の提案も行われた。
同説明会時点での各流通団体在庫点数は、呼びかけ団体のSSグループは当時メンバー数14社で在庫点数は12万点。九州部友会が6万点、ビッグウエーブが10万点、NGPグループが27万点、SAPグループが6万点、と報告されており、単純合計でも在庫点数は61万点となる。これらのデータを共通のホストコンピュータに取り入れるか直接接続かは別にして、7つの流通グループの会員が相互に保有データを利用できる計画だ。
ただ、設立基盤やその背景、経営理念が異なる各グループが、それぞれの計画に基づいて作り上げたコンピュータネットであり、ソフトもハードも異なる同士を結び付けようという構想だけに各種の困難が予想された。しかし、当時(1995年)の「コンピュータ技術からすれば、相互の転換技術に大きな問題はない」という工藤社長ら提案者側からの見解が示された結果、各グループのソフトの特色はそのまま残して、純粋に「在庫データのみをオンラインすることが可能ならば検討に値する」として同会合での大勢の雰囲気は「総論賛成」の様子であった。
市場の拡大と業界の発展という将来の見地からすれば提案への「賛同」は当然のように思えた。そして、提案者の工藤準備理事(SSグループ会長)を中心に検討していくこととなった。
第2回の会合は、95年10月11日の午前9時から東京都内の都ホテルで開催と決まった。同日は午後からリサイクル部品協議会の第5回準備理事会会合の日でもあった。
第2回の顔ぶれは前回同様。前回では主に構想の考え方、狙いなどが審議の中心だったが、当日は、新システム案の具体的機能、仕様についての案内と、各グループの組織としての考え方の表明が行われた。結論から言えば、A-JAPANの考え方は納得できる、だが各グループともに、独自のシステム開発に投資、まだ軌道にも乗っていないグループもあり、新たな開発費投資は難しい、というところが本音であった。NGPグループはグループ内の品質と他グループ商品の品質差が大きいとして加盟に反対だった。
工藤委員としては、折角の提案が潰えたことについて、その場では多くを語らなかったが、その後、彼自身、時とところを変えて再び「A-JAPANの復活を試みようとした」ことも事実である(旧15年史、pp. 161-164)。
実はこの後、1998年に通産省自動車から自動車補修部品の日米横断的な在庫流通ネットワークの計画が、協議会を含む自動車補修部品関係業界に提案された。しかし、これは国策としてのシステム構築であり、しかも日米横断的なシステムという夢の構想ではあった。しかし、最初は大風呂敷を敷いたものの、どんどん予算や計画の規模は縮小され、リサイクル部品(だけ)の国内在庫共有流通ネットワークの構築へと変わってしまった。いわゆる通産省主導のA-JAPAN構想である。自らのシステムに愛着を持つNGPは最初からこれに参加しなかった。当初は参加していたビッグウェーブも結局参加を取りやめた。そしてNGPもビッグウェーブも今世紀に入った直後に、一時協議会を退会してしまう。またA-JAPAN構想の生みの親でもある工藤氏が率いるSSGも、協議会の動きと一線を画し、結局当時カーコンビニクラブなども運営し、整備業者のネットワークの構築に成功しつつある翼システム(現ブロードリーフ)の、リサイクル部品流通システムの構築に一役買った。
結局通産省肝いりの自動車リサイクル部品ネットワークは、部友会、シーライオンズクラブ、システムオートパーツの他、新たに協議会に加盟した、テクルスネットワーク、ジャパンエコネット会(現在解散)によって利用されてきた。これがいわゆるJAPRAシステムである。
しかし、ITやAIがどんどん人間の経済に導入され、コンピュータが進化する中、JAPRAシステムのシステム更新が迫り、JAPRAシステムを利用するメンバーは、既存の他グループのシステム、具体的にJARAグループ等が使用していたATRSへの相乗りを図る。これを機に、一気にNGPやスーパーラインシステムを使用しているメンバーにも、既存のネットワークを尊重してお互いの在庫を見ながら、部品の販売もできるように作られたのが、現在のARPNであると考えられる。
(参考文献)
外川健一(2024)「日本の自動車中古・リサイクル部品生産・流通の特質と課題-中古部品流通ネットワークに焦点を当てて-」『産業学会研究年報』39、pp. 115-134。
平岩幸弘(2015)「自動車リサイクルの潮流第49回 “マルチ解体機”の発案と改良-豊富産業グループ・-高倉可明会長に聞く-(前編)」『月刊自動車リサイクル』49、pp.42-51。
平岩幸弘(2015)「自動車リサイクルの潮流第50回 “マルチ解体機”の発案と改良-豊富産業グループ・-高倉可明会長に聞く-(後編)」『月刊自動車リサイクル』50、pp.42-49。